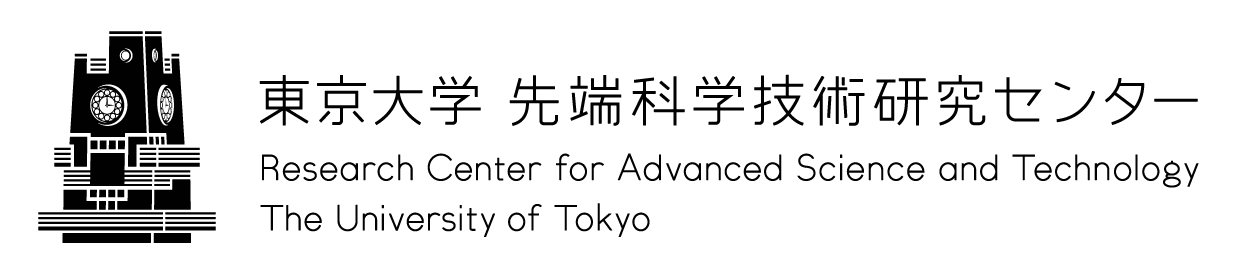サイエンス・芸術・デザインの多様性を生かした子供たちの育成
文理芸術の多様な角度から、サイエンス(理性)だけではなくアート・芸術を含めた感性も大切にし、理性と感性のバランスをもって、多様な感覚でモノやコトに対峙できる人間性と倫理観ある子供たちの育成、真のSTEAM教育を目指しています。
子ども自然探究教室の開催
2026年度「子ども自然探究教室」スケジュール
開催場所:東京大学先端科学技術研究センター3号館中2階セミナー室
開催日時:
① 4月11日(土)13:00-16:00(内容:カイコガの行動実験、フェロモンの抽出、顕微鏡観察、触角の電気を計る、筋電位でドローンを飛ばすなど)
② 6月5日(金):キャンパス公開にあわせて3号館南棟3階にて開催(参考内容:カイコガの行動実験、触角の電気を計る、筋電位でドローンを飛ばすなど)
③ 6月6日(土):キャンパス公開にあわせて3号館南棟3階にて開催(参考内容:カイコガの行動実験、触角の電気を計る、筋電位でドローンを飛ばすなど)
④ 9月12日(土)13:00-16:00(参考内容:カイコガの行動実験、フェロモンの抽出、顕微鏡観察、触角の電気を計る、筋電位でドローンを飛ばすなど)
⑤ 11月から12月ごろ:並木研究室との共同開催
⑥ 2月13日(土)13:00-16:00(参考内容:人や昆虫から生物電気を計る装置を作って、その信号でロボットを動かしてみよう!)
2025年11月15日(土)昆虫の不思議な行動を探る:触角・複眼・脳のかたちとはたらきを調べる(ご家族でお楽しみください!)(終了)
2025年 8月12日(火) 大昆虫展にて実験教室を開催 大昆虫展(終了)
2025年 3月22日(土)、29日(土):子ども自然探究教室@先端研(終了)
2024年 8月12日(月)~14日(水):夏のムササビ自然探究学校2024(終了)
2024年 6月29日(土):ムササビ自然探究学校 in 東大先端研(終了)
2024年 4月28日(日)、29日(月):春のムササビ自然探究学校 in 片品村花咲(終了)
2024年 4月 7日(日)昆虫と音楽とロボットの不思議な実験教室
小中高生を対象とした実験科学教室・講演会・研究室見学会
小中高生を対象に生物(特に昆虫)実験や、ロボット・プログラミング、研究所見学などの課題探究の実験や体験を通して、自然や科学の魅力を感じ、人も自然の一部であるという「こころ」を身につけ、これからのあるべき未来を一緒に考えていただくための活動を年に4回程度繰り広げています。
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)の次世代人材育成事業である「次世代科学技術チャレンジプログラム(STELLA)」を通して日本のSTEAM人材育成の推進を担い、多くの教育機関や教育関係者とともに活動しています。未来をになう児童や生徒に、科学という理性の大切さとともに感性の大切さを伝え、自分だけではなく他のものにも寄り添える子どもたちを育成していきたいと思います。
小中高生対象の実験科学教室や講演会、研究室見学会などをこれまでに200件以上開催してきました。
聴覚に障害のある生徒のみなさんも、筑波大学附属聴覚特別支援学校の教員のみなさまのご支援のもと開催してきました。現在も多くの教育機関や自治体からのご依頼に対応させていただいています。
これまでの活動リストはつぎのとおりです。活動リスト
謝辞:
この「子ども自然探究教室」は、教員とスタッフのボランティア活動として行われています。
本活動の一部は、ISCアドバイザーズ合同会社(渡辺健太様)のご寄付により行われています。
本活動の趣旨にご賛同をいただける方は、ぜひともご支援のほどをお願いいたします。
ご連絡は、神﨑亮平(kanzaki(at)rcast.u-tokyo.ac.jp)までお願いいたします。
昆虫と音楽とロボットの不思議な実験教室の一場面





近藤薫さんの演奏とおはなし




フェロモンのにおいはわかる?
子ども自然探究教室で計画中のICT教材
- マイコンプログラミング初歩編
- 筋電位計測と筋電位によるロボット制御ためのレッスン
- マイコンプログラミング・通信(Advanced)
- 筋電位を計測するためのアンプの作製
- 簡単なNode-redの使い方
- 筋電位処理プログラム(MQTT-Nnodered・グラフ表示)の作成
- 筋電位表示用のオシロスコープの作成
- 簡易Function Generator(筋電位表示のシミュレーション用)
- スマホでみれる遠隔カメラを作ってみよう
- チョロQをマイコンでコントロールするための改造
- 匂い(アルコールセンサ)を検知したら動くチョロQをつくってみよう
- ロボットカーを作ってみよう
- 匂い(アルコール)を検知したら動くロボットカーをつくってみよう
- 匂い(空気の質 VOC)は測るセンサーを作ってみよう
- ドローン(TELLO)とチョロQをジョイスティックや筋電位でコントロールしてみよう
- フィールドで複数の定点で温度・湿度センサ・人感センサの情報を無線で計測してグラフ表示しデータを保存するシステムをつくてみよう(高難易度)
検討中: