テーマ:Why war? ひとはなぜ戦争をするのか? Part II
日時:7月23日(水)15:30~17:30
会場:高野山大学黎明館
キーワード:先端技術と倫理、より良き生存、持続可能性、国際関係
セッション概要:人はなぜ戦争をするのか?―昨年7月の高野山会議、そして12月のサテライトシンポジウム「戦争における倫理と法」において、この現実的な課題を中心に討議が続けられました。ほぼ90年前の戦間期に、国際連盟の要請から生まれたアインシュタイン(物理学)とフロイト(精神科学)の往復書簡は、その後の原爆の開発(ルーズヴェルトへの進言)や、投下後の核廃絶の道(ラッセル・アインシュタイン宣言)へ直結していきます。皮肉なことに核抑止力によって戦後80年間は大国同士の戦争は起こりませんでした。この課題を巡る高野山会議での討議は、自然科学から社会科学・人文科学、さらには宗教・芸術の視座も含めて進んでいます。
世界の状況は大きく変わりました。歴史的には複雑な背景がありますが、国際法を無視した侵略によって、この一年間にも極めて多くの無辜の命が奪われました。国際連合も、大国が互いに拒否権を行使するために、平和への倫理と法がその力を発揮出来ない現実があります。一方で、国際刑事裁判所は、侵略を続ける両国の首脳に対し国際法上の戦争・人道上の罪による逮捕状を発出し、条約締約125か国への入国が実際に制限されています。
「個人倫理」と「社会倫理」の相克も、先回指摘された重要問題です。これまでの討議から、自然科学と社会科学・人文科学の考え方の特徴と、その差も見えてきました。自然科学が扱うようなパラメータ(媒介変数)の数が少ない課題には厳密な演繹的アプローチが可能ですが、人間社会に発生するパラメータ数が多い課題には帰納的なアプローチが求められます。これは、共創(協創・響創)が難しい理由でもあります。異分野の連携・協力によって演繹と帰納を交互に繰り返しながら、漸近的に仮説的推論(アブダクション)の解を求めることは可能でしょうか? 逆問題を解けるでしょうか?
さらに熟慮すべきは、現生人類の数千年から数万年の歴史の中で、現在はかつてない転換期にあるという歴史学者からの指摘です。かつて人類が経験したことがない現在の情報化社会では、新しい生物学と情報技術の本質を探るのは勿論ですが、物質と情報から構成される地球システム・社会システムを、エネルギーとエントロピーの両視座から複合的に理解することが求められています。自然(じねん)の理解と、そこに生かされる自己と他者の共存・共生(ともいき)が問われていると考えられるのです。
「1200年後の世界」との関わり:安寧とより良き生存を目指すべき人類はその誕生以来殺し合いを続け、科学技術が高度に発展した現在も戦争のない世界は実現できていません。それどころか、核兵器により人類の戦争が地球全体を壊滅させる危機が顕在化しています。科学技術の進歩に対応した「新しい啓蒙」を発展させ、人間中心の世界観から、人間が自然の一部として調和を目指す世界観を構築することで、私たちは1200年後の世界を考えるための入口に立てるのではないでしょうか。
登壇者(統括:杉山 正和)

杉山 正和 Masakazu Sugiyama 東京大学先端科学技術研究センター所長・教授(エネルギーシステム分野)
専門はエネルギーシステム分野。2000年、東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻博士課程修了。博士(工学)。2016年、東京大学大学院工学系研究科教授、2017年より東京大学先端科学技術研究センター教授、2022年4月より所長を務める。

梅若 ソラヤ Soraya Umewaka 起業家 / マルチメディアアーティスト(映像作家, 演出家)
初舞台3歳(仕舞「猩々」国立能楽堂)。プリンストン大学卒業(政治学専攻)。映画作家として国際映画祭での上映歴多数。2019年にパナソニックセンターでマルチメディア現代能『地獄の門を叩く男』を演出・監督(主催:ブラジル大使館)、2022年に株式会社虎屋と新作能『月の舞』を制作 (2022年)。映像・音楽・ゲーム分野のクリエイターをつなぐウェブプラットフォーム「MatchHat」を創設した。

大倉 源次郎 Genjiro Okura 能楽小鼓方大倉流十六世宗家、(公社)能楽協会副理事長/重要無形文化財保持者(人間国宝)
能楽小鼓方大倉流十六世宗家、(公社)能楽協会副理事長。1957年大倉流十五世宗家・大倉長十郎次男として大阪に誕生。1981年甲南大学卒業 、1985年宗家継承、2017年重要無形文化財保持者各個認定 、観世寿夫記念法政大学能楽賞受賞。2024年2月(公社)能楽協会パリ・オリンピック能楽公演参加、25年6月大阪関西万博「日本経済新聞社メディア事業伝統文化未来共創プロジェクト」に参加。多数の制作・活動を行っている。

小泉 英明 Hideaki Koizumi 東京大学先端科学技術研究センターフェロー
1971年東大基礎科学科卒業日立製作所入社、1976年東大理学部に論文提出し理学博士。
量子物理学で超高正確度・高感度の元素分析法を創出。開発装置は世界一万数千箇所で稼働。水俣病解明や公害・環境分析に寄与。国内初の超電導MRI装置や世界初の光トポグラフィ装置を開発し国内外の病院に設置。人体の形態と機能(特に脳)の解明や臨床に寄与。日立基礎研究所第4代所長、日本分析化学会第55代会長。論文・著作多数。

中井 遼 Ryo Nakai 東京大学先端科学技術研究センター教授
早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程修了。博士(政治学)。専門分野は比較政治(選挙・政党・世論,ナショナリズム,欧州政治,バルト諸国政治)。近年は環境争点やエネルギー争点をめぐる政治意識にも関心。日本学術振興会特別研究員,立教大学助教,北九州市立大学准教授等を経て現職。主著に『デモクラシーと民族問題』(勁草書房),『欧州の排外主義とナショナリズム』(新泉社)など。
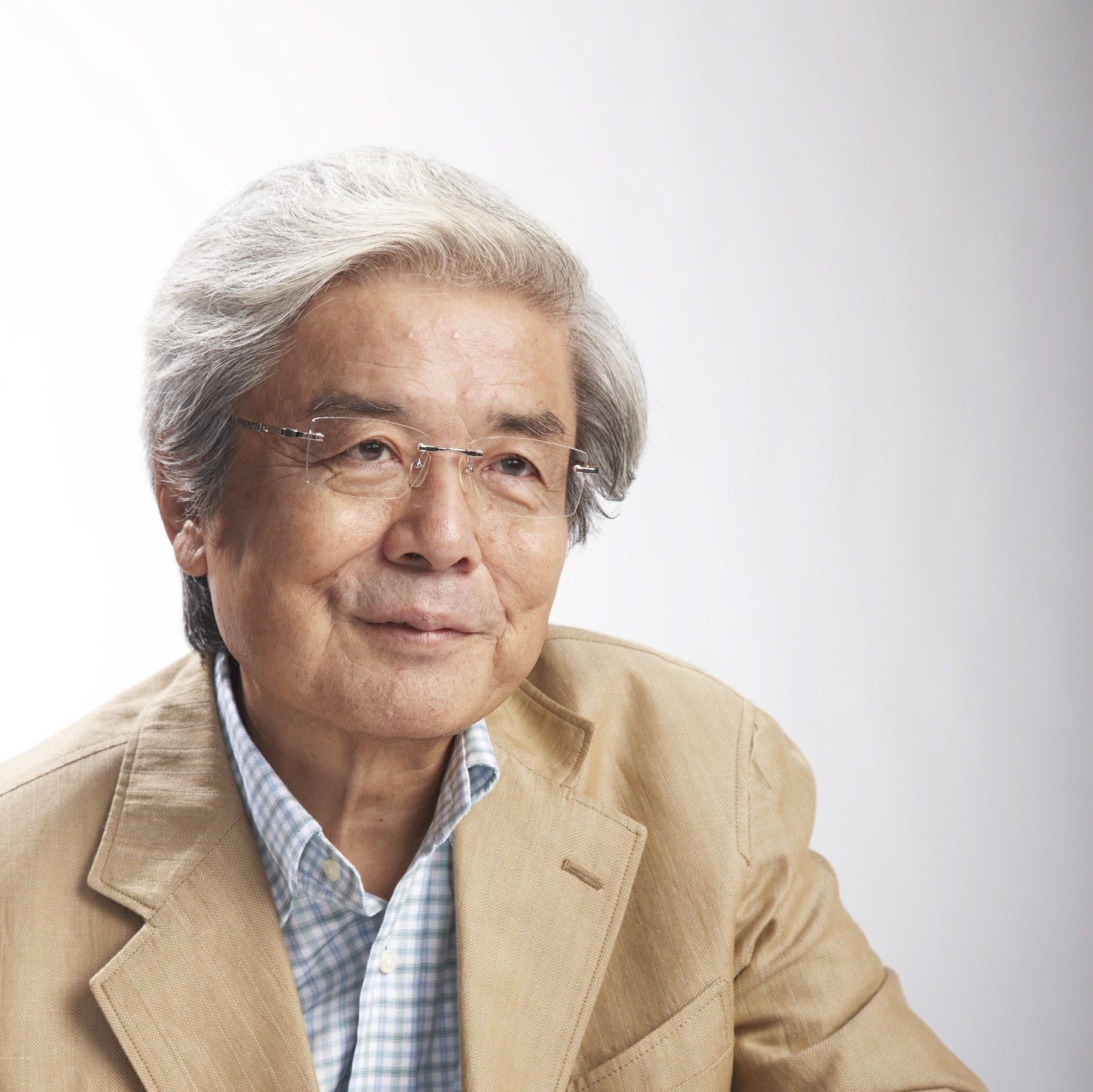
養老 孟司 Takeshi Yoro 解剖学者、東京大学名誉教授
1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生まれ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。1989年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。2003年の『バカの壁』は450万部を超えるベストセラーとなった。ほか著書に『唯脳論』『ヒトの壁』など多数。
